刑法・その1
こういうことを書くと学年が分かってしまうのだが、最近、刑法総論の勉強を始めた。
刑法というのは、法学の中でも学説の対立が熾烈を極めている分野らしいが、一体それってどうなのか、と疑問に思ったので書いてみる。
なお、以下に続くのはあくまで初学者の意見なので、そのまま真に受けることのないよう、よろしくお願いします。
上にも書いたように、刑法学というのは数ある法分野の中でも色々な学説が乱立している。
刑法の解釈でも何が犯罪となり、あるいはならないかは、学説によってまちまちなところもある。
既習者の方にはなじみが深いと思われる、違法性論における「結果無価値論」や「行為無価値論」、「二元論」などが対立の代表例であろう。
このように刑法の解釈として色々な説が成り立つ背景には、刑法という法律の持つ性質がある(らしい)。
つまり、刑法とは時に人の生命、自由、財産を奪うという強烈な効果があるわけで、使い方を違えると大変なことになる。
このような強烈な効果がある以上、アバウトな解釈はすべきではなく、色々な理論を闘わせることに合理性を見出すこともできる。
しかし、そのような強烈な効果(刑罰)を持つ以上、刑罰の要件となる犯罪についても、何が犯罪となるのかを厳格に定義しておく必要があるだろう。
このように、犯罪と刑罰を法律によってあらかじめ決定しておき、それに意図的に反した者に制裁を加えることを「罪刑法定主義」という。刑法を学ぶと最初の最初に習う概念である。
ここからが僕の意見なのだが、じゃあ学会でも統一見解のない学説の下で、罪刑法定主義がきちんと成り立つのだろうか。今後も諸説の林立が続くということは、「何が犯罪で何が犯罪でないか」が、グレーゾーンの範囲のみにしろ、確定しないということではないのか。それならばいっそ、特定の有力説を採用することを刑法典に明文で書いてやったらどうなのか。
確かに、判例の積み重ねによってグレーゾーンを埋めればいい、という意見もありそうだが、判例には法律ほどの拘束力はないし、判例と違う立場を下級審が出すことも結構あるらしい(最高裁による判例変更というのもあるし)。
また、前述したように刑法の強烈な効果にかんがみて、まだまだ議論を煮詰めるべきだという意見もあるかもしれない。しかし、理論対立であれば、短くても100年近く、長けりゃ数百年にわたってやってるんじゃないですか、と問いたい。
まあ、このような主張を僕がする深層心理として、ヤケに説が多くてめんどいなあ、という思いがあることを否定するつもりはないのだが。
実際どうなんでしょうか、トラックバックかコメントで教えて下さい。詳しい人。
2回連続で出すのもどうかと思うけど、上の話に「ふーん」と思ったらクリックしてもらえるとうれしいっす。






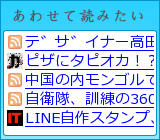


0 コメント:
コメントを投稿